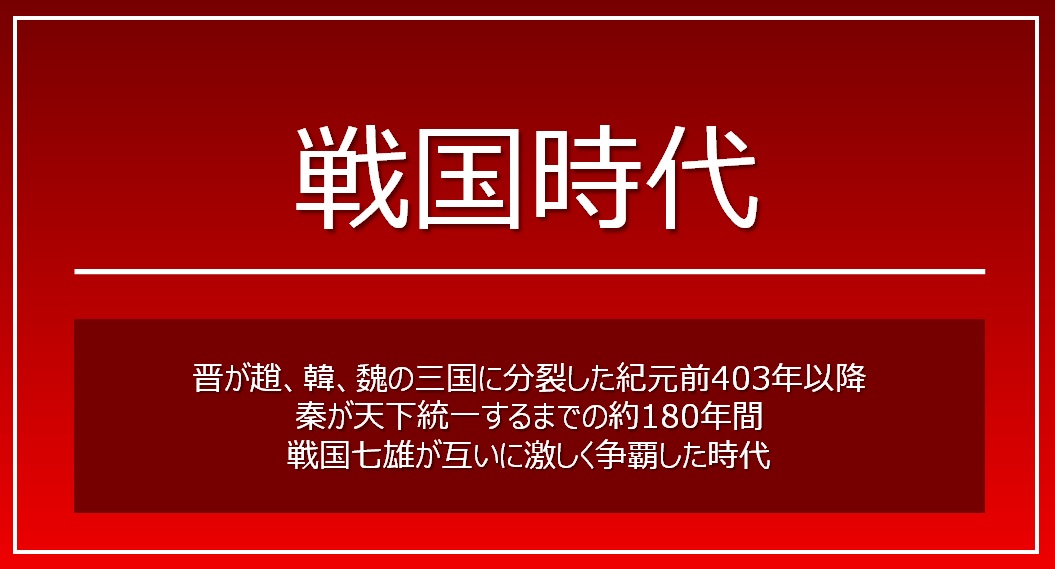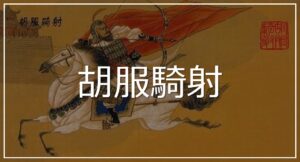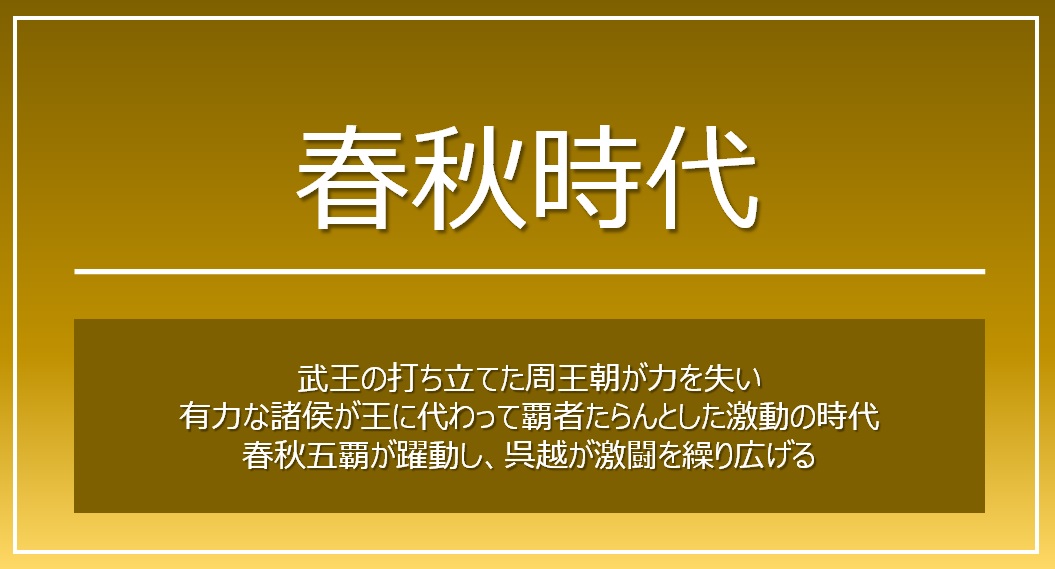- 前漢時代の学者である劉向が編集した『戦国策』(紀元前476年から紀元前222年まで約250年間にわたる時代に存在した各国の国策や逸話をまとめた書物)の書名に由来する。
- 戦国時代に覇を競った有力国(紀元前403年に誕生した趙、魏、韓に加え、春秋時代からの大国である燕、斉、楚、秦の4国の計7国)は、戦国七雄と呼ばれる。
- その他の小国は、七雄の勢力争いの中、服従するか、滅ぼされるかなどで淘汰されていった。
- 戦国七雄の中で最も早く国力を高めたのは魏であった。初代君主の文侯は李克や呉起などの文武において優れた人材を集めて急速に強大化し、隣国の秦や斉、趙に圧力をかけるようになった。
- 斉は紀元前388年に宰相・田和がクーデターを起こし、君主・康公を幽閉して国政を一新する。さらに、紀元前341年の馬陵の戦いで名将・孫臏の活躍により魏に大勝して、強国として名乗りを上げた。
- 秦は孝公の時代に登用した商鞅が法治主義を進める改革を行い、国力を高めることに成功し、馬陵の戦い以降、勢いを失った魏を破って領土を拡大した。
勢力分布図
.jpg)
| 秦 | 周代から続く西の大国で、春秋時代には五覇の一人穆公を出すほどの強勢を誇った。穆公の没後は一時的に国力が衰えたが戦国時代に再度勢力を挽回し、嬴政の時代に他の六国を攻め滅ぼして天下統一した。 |
| 楚 | 春秋五覇のひとりを出した、広大な国土を誇る南の大国。隣国の秦との対立が続き、紀元前278年には秦の将軍・白起によって遷都を強いられる。その後も魏や趙と連携して秦と戦うが退けられ、紀元前223年に滅亡した。 |
| 斉 | 紀元前386年に田氏が春秋時代の強国・斉を滅ぼして立てた国家。田斉とも呼ばれる。兵家の代表者・孫臏を登用して勢力を拡大したが、燕の楽毅率いる五国連合軍に滅亡寸前まで追い込まれ、紀元前221年に秦に滅ぼされる。 |
| 燕 | 周代から続く国家だが、紀元前315年に斉の侵攻を受けて一時的に滅亡。紀元前313年に昭王が立ち復興し、名将・楽毅の活躍により勢力を拡大した。その後、秦王・嬴政に刺客を送ったことで怒りを買い、紀元前222年に攻め滅ぼされた。 |
| 趙 | 晋の分裂によって誕生した国家。武霊王の時代に胡服騎射を取り入れて軍事強国となり勢力を拡大したが、武霊王の没後は衰退を続ける。紀元前260年の長平の戦いで秦に大敗して大きく国力を損ない、紀元前228年に秦に滅ぼされた。 |
| 魏 | 晋が分裂して立った三晋の一つ。名君・文侯のもとで国力を高め戦国時代初期の最強国となったが、斉や秦の侵攻を受けて衰退した。秦が大国となってからは圧力を受け続け、紀元前225年に滅亡した。 |
| 韓 | 紀元前403年に独立した三晋の一つ。七雄の中で最も勢力が弱い時代が続いたが、名臣・申不害の手腕により一時的に国力を高めた。しかし、申不害の死後は隣国の秦の圧力に悩まされ続け、紀元前230年に六国の中で最も早く滅亡した。 |
縦横家の活躍
戦国時代は諸国を旅して諸侯に面会し、強国となるための策を提案する説客たちが多く活躍した時代でもある。この説客たちは別名として縦横家とも呼ばれ『戦国策』にも多くの逸話が収められている。その中で代表格は蘇秦と張儀の二人の存在である。
| 合従 | 連衡 |
|---|---|
| 蘇秦 | 張儀 |
| 秦以外の六国が同盟して秦に対抗する。 | 秦がそれぞれの国と個別に外交し、和睦や服従させる。 |
| 最初、秦の恵文王との会見に望むが受け入れられなかったので、燕に向かい、生き残る策として趙との同盟を提案して成功させた。続いて、韓、魏、斉、楚の王と面会してこれらの国との同盟も成立させ、当時最も勢いのあった秦に対抗する六国同盟を完成させた。 | 無名の時代に蘇秦を頼った際に侮辱を受けたため、その屈辱を糧に秦に仕官して合従策への対抗策として連衡策を提案した。六国それぞれと個別に外交を行って秦との同盟を成立させるものであり、まず魏王を説得して同盟させて、楚、韓、斉、趙、燕と同盟を結び、対秦同盟を崩壊させた。 |
制度改革
各国はこれまでの枠組みを打破するような改革を進めて、躍進を遂げていくのである。
王族でも功がなければ財産を没収されるくらい厳格な法整備により古き野蛮な時代からの転換をして法治国家として生まれ変わることになる。相当に厳しく改革を進めたので、既得権益を手放さざるを得なかった貴族たちの強い恨みを買い、商鞅は激しく憎まれた。
趙は領土の北側が遊牧民族の生活圏に接していて抗争が絶えなかったが、武霊王は遊牧民族の風習に学び強力な軍隊をつくる方法を考えつき、これに基づき「胡服令」が発令された。この画期的な軍政改革により軍事力が急激に成長し、隣国の中山国を攻略して領土拡大に成功する。
内戦に乗じて侵攻してきた斉によって、一時的に斉の支配下にはいるが、昭王が即位すると、人材を集めるために郭隗の言に従って重用した。するとその噂が広まり、燕に活躍の場を求めて、楽毅や鄒衍などの優秀な人物が仕官してくるようになった。こうして燕の再建を進め、斉へ報復するための準備を進めた。
戦国四君の時代
戦国時代の後期には、国王以上に影響力を持ち、その名声を利用して他国との連携を成立させる外交面で貢献した4人の人物がいた。それは、斉の孟嘗君、楚の春申君、魏の信陵君、趙の平原君である。いずれも、莫大な財産を有し、数千人のぼる食客を養っていたとされ、その名声は各国の王を凌ぐほど高かったと伝えられている。
戦国時代に始まった風習とされる。資産家に客として養われていた人物のことをいう。多くは主人に対して強い恩義を感じており、有事の際には任侠の志をもとに、自らの命すら投げ出して働く者もいたようである。当時、食客を多く抱えていることが、その人物の名声につながっていた。
しかし、あまりにも影響力が大きかったので、次第に王に疎まれるようになり、平原君以外は最終的に国政から排斥されている。